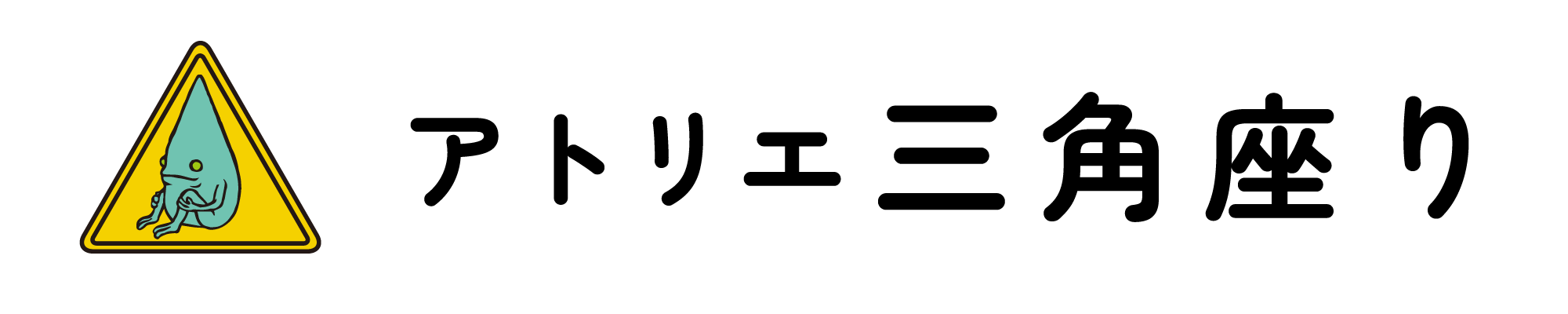みなさまこんにちは!
私安東睦郎は造形教育の仕事の傍ら、狂言役者としての活動もしていまして、近々公演があるので宣伝させて頂きます。
「室町の笑い その12 諍い編」
演目は「土筆(つくづくし)」と「佐渡狐(さどぎつね)」の二番です。
諍い編ということで、バトルがテーマの狂言二番。狂言は喜劇ですのでちょっとバカバカしい小競り合いで笑っていただければ幸いです。

◯狂言ってなに?
見たことがない方にとって、狂言と聞くと、「伝統芸能やし、なんか難しそう・・・」と思うかもしれません。ちょっとでも親しみやすく感じてもらうために3つのポイントを書かせて頂きます!
①狂言は室町時代のコント!
狂言は大体20〜30分、演者は2〜3人で演じられる喜劇、コメディです。当時の民衆の失敗談や、身分が下の者が偉い人をからかったり、そういったお話を笑いに変えてお届けする演劇です。
600年前の人々が何を面白いと感じたのか、意外と現代に生きる私たちと共通の感性を持っていたり、反対に今だと笑えないような内容だったり・・・。
室町時代の情景を思い描いて楽しむタイムマシン!
室町時代と現代を、笑いという架け橋でつなぐ、そんな芸能です。
②話し言葉だからわかりやすい!
「古い言葉の意味がわからないんじゃないのかな・・・?」と心配になる方も多いと思います。
狂言の台詞の大半は口語体、つまり当時の民衆が街中で実際に使っていた言葉で演じます。口語体の反対は文語体ですが、こちらは後世に文書として残す、堅い言葉で書かれています。狂言の兄弟、能は文語調で演じられる悲劇です。普段日本語を話す私たちなら大体80%は理解できると思います。
もちろん現代で使わない言葉の表現や言い回しはあります。その理解が難しい言葉は幕間に解説させて頂いたり、演者の身振り手振りで文脈から汲み取って楽しんでいただけると思います。
余談ですが年一回日本に来た留学生に向けて公演する機会があるのですが、わからない言葉が多くてもみんなケタケタ笑ってくれます。
③想像力で楽しむ!
狂言を演じる時に使う道具は、本当に必要最低限です。扇子を盃に見立ててお酒を酌んだり、鬘桶(かずらおけ)と呼ばれる蓋つきのバケツを椅子にしたり木に見立てたりします。舞台も劇団四季のような大きな書き割りなどは無く、背景に松が描かれた約5メートル四方の何も無い空間で演じます。
舞台の上で演者はパントマイムのように扉を開ける仕草や、木に登る仕草をします。「広い野原にやってきた」という台詞と共に客席を遠く大きく見回したりします。何も無い舞台だからこそ、演技次第でどんな場所にでも変身するのです。お客さんもそんな演技を見て想像することが、狂言を楽しむコツなのかもしれません。
いかがでしょうか、少しでも狂言に興味を持っていただけたら幸いです。
もし公演のご予約をご希望でしたら、チラシ掲載の番号にお電話いただくか、
当HPのお問合せフォームに
・お名前
・人数(大人と中学生以下の内訳)
・メールアドレス
を記載の上お送りください。
料金は当日現金精算でご対応しております。